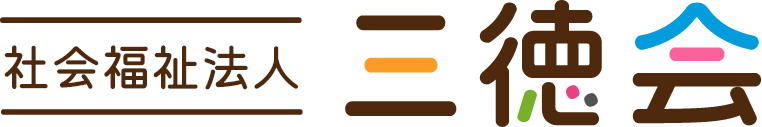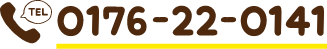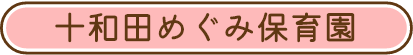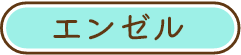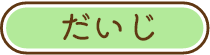イベント
2025.06.25
総合防災訓練🧯放水開始!
今日は、地震発生後の火災を想定した総合防災訓練を行いました🧯 十和田消防本部の方々にご協力・ご指導をいただきながら、より実際に近い状況での避難を経験することがで...

日常の様子
2025.06.24
夏だ!プールだ!!
夏を前に、園のプールをうぐいす組の子どもたちがお掃除してくれました。 「ここ、まだ汚れてるよ!」「こっちはピカピカだよ!」と声をかけ合いながら、雑巾を手に、隅か...

日常の様子
2025.06.18
「あじさいゼリー」で涼やかおやつタイム
今日のおやつは、6月ならではの「あじさいゼリー」でした。 透き通った水色と紫のクラッシュゼリーは、見た目も涼やかで、この時期にぴったり。 大きいクラスの子どもた...

イベント
2025.06.16
COW飼う’Sとひまわり植え
先日、三本木農業恵拓高校で牛の研究をしている「COW飼う’S(カウカウズ)」の高校生のみなさんと一緒に、うぐいす組の子どもたちが園のひろばにひまわりの苗を植えま...

イベント
2025.06.10
運動会!
青空の下、今年も運動会を開催しました✊ 子どもたちは、それぞれが「ちょっとだけ難しいこと」にチャレンジ。 ドキドキしながらも、仲間と一緒に力いっぱい取り組む姿が...

2025.04.21
🌸春の桜と鯉のぼり🎏
十和田の桜も満開になり、官庁街通りはたくさんの人が歩いていますね😄 十和田めぐみ保育園には、園庭に大きな桜の木があります🌸 今年もたくさんの花を咲かせてくれてい...