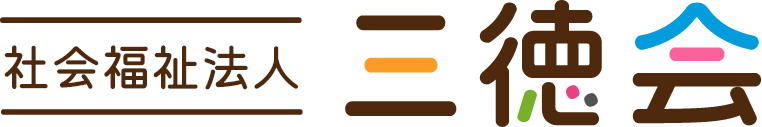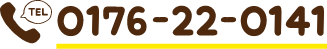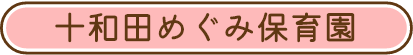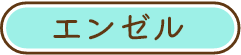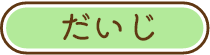「これ、なあに?」
子どもの絵や工作を見て、思わずそう尋ねたことはありませんか?大人の目から見るとよくわからない線や形に見えても、そこには子ども自身の思いや気づきが込められています。

認定こども園教育・保育要領では「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、感性や創造性を育む」ことが表現の領域に掲げられています。つまり「表現」とは、完成品の上手・下手を競うことではなく、子どもの内面が外にあらわれる大切な営みなのです。

子どもの表現には、大きく二つの柱があります。ひとつは自由に思いつきを形にする創造性(クリエイティビティ)。もうひとつは、筆を持つ、はさみを使うといった技術の向上(手指の器用さや素材の扱い方)です。この二つの柱が車輪のようにバランスよく回ることで、子どもたちの表現はぐんぐん広がっていきます。

たとえば、2歳児が大きな紙に思いきりクレヨンで線を引く姿を思い浮かべてください。大人からすると「ぐちゃぐちゃ」に見えるその線は、「動かしてみたい」「やってみたい」という表現欲求そのものです。その経験を重ねていくうちに、「もっと丸く描けるかな」「色を混ぜたらどうなるだろう」といった工夫へと発展していきます。そこに、創造性と技術の両方の成長が見えてきます。

作品展は、そうした日々の積み重ねを一望できる場です。だからこそ、保護者の皆さんにお願いしたいのは「答えを探さずに、一緒に味わうこと」。
「これは○○の絵?」と決めつけるよりも、「楽しそうに描いたね」「この色を選んだんだね」と声をかけいただけると嬉しいです。子どもは自分の表現が認められたことを実感し、さらに挑戦する意欲にも繋がります。

私たちも、子どもたちの「やってみたい」を大切にしながら、技術を少しずつ身につけられるよう心がけていきたいと思っています。作品展はその成果を“比べる場”ではなく、“子どもの今を見ていただく場”。
ぜひ、お子さんの作品に込められた心の動きを、まっすぐに感じ取っていただければと思います。
次回は「自然との出会いが育む感性」について。外遊びや自然素材との関わりが、子どもたちの表現をどのように育てていくのか、一緒に考えてみましょう。