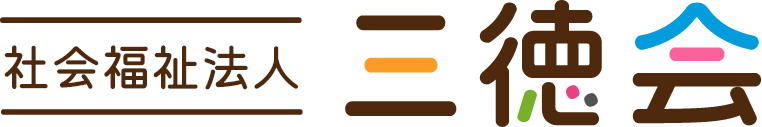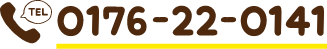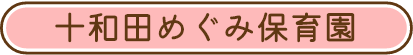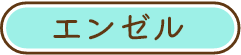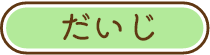子どもは毎日、五感を通して世界を感じ取っています。耳に入る音、目に映る色、手に触れる感触──そのすべてが子どもの心を動かし、表現のエネルギーとなっていきます。

認定こども園教育・保育要領でも「感じたことや考えたことを自分なりに表現すること」を大切にしていますが、その出発点はやはり「感じること」にあります。

たとえば、太鼓を叩いたときのドーンという音の響き。子どもはその大きさや振動に驚き、同時に「もっとやりたい!」という意欲が湧きます。音の強弱やリズムを工夫する中で、自分なりの音楽表現が生まれていくのです。

また、絵の具を指でぬり広げるときの、ひんやりとした感触や、色が混ざって変化していく様子。最初は偶然に生まれる模様ですが、それを「きれい!」「ぶどうジュースみたい」と受け止めることで、子どもの表現はさらに広がっていきます。

粘土遊びや砂遊びでも同じです。丸める、ちぎる、積む。そうした感触の体験は、子どもの指先の器用さを育てると同時に、「作りたいものを形にする力」につながっていきます。

大切なのは、大人が結果を決めつけないこと。「これはお花?」と尋ねるよりも、「ふわふわしてるね」「いろんな色が重なってるね」と、子どもの感覚に寄り添う言葉をかけてみてください。子どもは「感じたことを大事にしていいんだ」と安心し、さらに挑戦する意欲を持つようになります。

作品展に並ぶ作品の中には、「何を描いたのかよくわからない」ものもあるかもしれません。でも、それこそが五感を使った自由な表現の証です。色や形をどう感じ、どう楽しんだか。そのプロセスにこそ、子どもの豊かな成長が表れています。

次回は「表現するって楽しい! ― 創造性と技術の両輪」。子どもの“やってみたい”気持ちと、“少しずつ身につく力”の両方を大切にする視点をお伝えします。