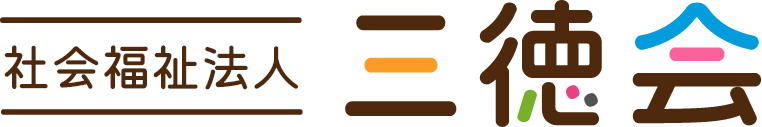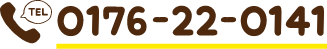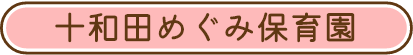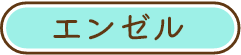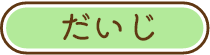子どもたちが夢中で描いたり作ったりしているとき、その表情は本当に生き生きとしています。「できあがったもの」よりも、「作っている時間」そのものを楽しんでいるのが伝わってきます。

教育・保育要領の表現領域が大切にしているのは、まさにその“楽しさ”。表現とは「自分を自由に出してみること」であり、それができるとき、子どもの心は解き放たれます。
同時に、表現は「技術」とも切り離せません。筆を持って線を引く、はさみで紙を切る、粘土を丸める──そうした動作の積み重ねは、子どもにとって技術を磨く大切な経験です。創造性と技術、この二つが一緒に育っていくことで、子どもの表現はより豊かになっていきます。

たとえば、4歳児が「ロボットを描きたい!」と思ったとします。最初はただ四角や丸を並べるだけかもしれません。でも、少しずつ体のパーツを分けて描けるようになり、色を塗り分ける工夫も出てきます。「やりたい!」という創造性に、「できる!」という技術が重なったとき、子どもの表現は飛躍的に広がります。

逆に、技術だけを重視してしまうと「上手に描けなかったからイヤ」と表現の楽しさを失ってしまうこともあります。大事なのは、創造性と技術が偏らずに支え合うこと。園でも、自由に描く時間と、少しずつ道具の扱いを覚える活動の両方を取り入れています。

作品展に並ぶ作品も、その“両輪”の成果です。上手・下手という基準で見てしまうと、子どもの頑張りや工夫が見えなくなってしまいます。でも、「ここに工夫があるな」「ここはやりたかったんだな」と目を向けてみると、子どもの表現の広がりを感じられるはずです。

保護者の皆さんにもぜひ「うまく描けたかどうか」よりも、「どんな気持ちで取り組んだのか」「どんな工夫が見えるのか」を探してみてほしいのです。その視点で作品を見ると、子どもが作品を通して語っている物語が、きっと見えてきます。

次回は「物語の世界でひろがる想像」。ごっこ遊びやストーリーテリングが子どもの表現とどうつながっていくのかをご紹介します。